
東京 練馬 訪問診療 内科 比較ナビ 優秀 訪問診療 内科 ランキング を交え基礎知識、選び方のポイントまで紹介 オンライン診療も
執筆中
- 訪問診療の内科って?
- どんな病気を診てくれるの?
- 自宅まで訪問してくれるのですか?
- 費用は保険適用内ですか?
- 訪問診療の内科によりどんな差があるの?
- どういった方が利用されているの?
- 外来も行っているのですか?
- 電子カルテとは?
- 訪問診療の内科のメリットをズバリ教えてください
- 診て貰えるのは内科だけですか?
- オンライン診療も可能ですか?
- 在宅医療って何ですか?
- 支援制度などもあるのですか?
- 現在の医療ニーズはどう変わっていますか?
- こんな症状は訪問診療の内科へ
- メンタル不調も見てもらえますか?
- 診療時間はどうなっていますか?
- 訪問診療の内科が患者様にできること
- 現代美の意識が上がっているのは何故ですか?
- 訪問診療の内科 利用者の声
ランキング
1位: L&P クリニック練馬院 内科 訪問診療

L&Pクリニック練馬院は、東京都練馬区大泉町にある地域密着型の医療機関で、内科、皮膚科、アレルギー科、精神科、心療内科を中心に診療を行っています。
訪問診療にも力を入れており、通院が困難な方への在宅医療サービスも提供しています。
L&Pクリニック練馬院は最新のIT技術を駆使し、患者さんに寄り添った便利で効果的な医療をお届けしています。
患者様の診療情報はデジタル化され、医療チームとのリアルタイムな情報共有が可能となります。
訪問診療では、患者さんの自宅や施設で必要な医療を提供します。
地域の方々の健康と生活の質の向上を目指し、個別のニーズに合わせたケアを提供しています。
皮膚科では、皮膚トラブルや美容に関する問題に対して最新の治療法と技術を活用し、お肌の健康と美しさをサポートします。
L&Pクリニック練馬院は地域の皆様と共に歩み、信頼と安心を大切にした医療を提供し患者さんの健康と幸福を第一に考え、質の高い医療を提供する医療機関です。
L&Pクリニック練馬院の特徴
最新のITを活用した医療
電子カルテやオンライン診療を導入し、リアルタイムの情報共有や遠隔診療を実現。
最新医療機器も活用し、患者様の診療品質向上に取り組んでいます。
技術の進歩に常に対応し、安心・安全な医療を提供します。
患者さんごとに合わせた医療の提供
在宅医療は入院治療の劣化版ではなく、個別に合わせた「カスタムメイドの医療」です。
病院は疾病治療を目的とし、患者の生活は特殊な環境です。
しかし、在宅医療は患者の日常生活を重視し、自宅で安心して治療を受けられるようサポートします。
医療行為だけでなく、患者の生活を支援し、患者や家族の悩みに寄り添うことも重要です。
それによって、入院治療の劣化版ではなく、患者の希望を実現するためのカスタマイズされた医療が提供されます。
皮膚科では、保険・自費診療対応
治療の選択肢を増やして、患者さまひとりひとりにとって満足のいく、最適な治療をご提供できるように、当院では保険診療だけでなく自費診療も行なっています。
L&Pクリニック練馬院では、患者様の健康と幸福を第一に考え、質の高い医療サービスを提供することを使命としています。
内科をはじめとする総合的な医療を通じて、患者様の病状を正確に把握し、最適な治療プランを提案しています。
また、訪問診療により、ご自宅や施設での医療ニーズに応え、安心して治療を受けていただけるよう努めております。
患者様の生活環境や個別の要望に合わせ、きめ細かなケアを提供いたします。
皮膚科では、皮膚トラブルや美容に関するお悩みに対して、最新の治療法や技術を駆使し、お肌の健康と美しさをサポートいたします。
患者様一人ひとりのご要望や状態に真摯に向き合い、最善の医療を提供するL&Pクリニック練馬院は今後医療の中でも中心的存在となっていくでしょう。
診療科目と特徴
内科:一般的な内科診療に加え、腎臓内科、糖尿病内科、循環器内科、呼吸器内科など幅広く対応
皮膚科:皮膚トラブルや美容に関する問題に対し、最新の治療法と技術を活用
アレルギー科:アレルギー性疾患の診断・治療
精神科・心療内科:心の健康に関する相談・治療を提供
訪問診療:通院が難しい患者様への在宅医療を実施
診療時間
月・火・金
9:00〜12:00 13:00〜17:00
水(第1・3・5週)
9:00〜12:00 13:00〜17:00
木・土・祝 休診 休診
日 10:00〜15:00(※)
休診
※日曜日は休診日ですが、依頼があれば診察可能です。診察希望の場合はご連絡ください。
院長
飯島 隆太郎
プロフィール
帝京大学医学部卒業
2015年 帝京大学医学部附属病院 初期研修
2017年7月–2021年9月 帝京大学ちば総合医療センター 第三内科(腎臓)
2021年10月 おおふな皮ふ科開設
2023年3月 医療法人社団L&P Medical設立
L&P クリニック練馬院 内科 訪問診療
https://l-p-clinic.com
〒178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目28−2
03-3924-0101
駐車場:無料駐車場あり(3台分)
▲目次に戻る
2位:城北さくらクリニック

城北さくらクリニックは、東京都練馬区にある在宅医療を中心としたクリニックです。
2012年(平成24年)10月に在宅療養支援診療所として開設して以来十数年が経ちます。
現在では各科内科医9名、精神科医、皮膚科医、当直医3名など医師合計14名となり、多くの看護師、相談員、事務スタッフが勤務する診療所となりました。
城北さくらクリニックは、複数の医師体制やいくつかの条件を満たし、※機能強化型在宅療養支援診療所、在宅緩和ケア充実援診療所として、快適な個々違うご自宅や施設での生活サポートに努めています。
※機能強化型在宅療養支援診療所とは??
城北さくらクリニックは「機能強化型在宅療養支援診療所」です。
24時間365日の連絡体制、往診および看護体制が整っていること、緊急時の入院受け入れまたは連携医療機関への入院手配ができること、さらにお看取りの実績や報告があること、などの厳しい基準をクリアした医療機関に認可される診療所のこと。
城北さくらクリニックが行う訪問診療は、通院が困難な患者様に対して医師がご自宅へ定期的に訪問して診療を行うことです。
病気の治療・予防を中心に行い、緊急時には24時間365日対応いたします。
病状に応じて、連携病院先への入院紹介や、毎週の訪問など訪問頻度を増やして、ご自宅での治療など適切に対応いたします。
病状が安定した方も治療が必要な方も親身に相談乗っていただけます。
在宅医療の対象となる方はお一人で通院が困難な方が対象となります。
例えば、
認知症や寝たきりで通院することが難しい方
ご自宅での終末期医療・緩和ケアを希望される方
退院後、ご自宅または施設での療養をご希望される方
ご自宅または、施設にて医療処置の必要な方
パーキンソン病やALSなどの難病を抱えている方
ご自宅で自分らしく過ごしたいとお考えの方など、様々な理由でご自宅での療養を希望される方を城北さくらクリニックはサポートします。
様々な理由でご自宅での療養を希望される方も城北さくらクリニックはサポートします。
城北さくらクリニックでは、患者様ご本人とご家族に安心して生活していただくために、24時間365日対応のコールセンターを設置しています。
患者様のご自宅には、コールセンターに簡単につながる専用の緊急端末「あんしんケータイ」を無料で貸与しています。
日常の不安や困りごと、治療のことなど、365日対応いただける心強い存在です。
城北さくらクリニックでは
経験豊富な医師・看護師・コーディネーターによるチームケア、医療機器の管理:在宅酸素、点滴、胃ろう、膀胱カテーテルなどに対応、終末期医療(がんの緩和ケア・看取り)に対応可能。
診療内容は、
内科全般
糖尿病、高血圧、心疾患、脳卒中後遺症などの慢性疾患管理
認知症ケア
褥瘡(床ずれ)治療
緩和ケア(がん・非がん問わず)
在宅点滴、医療機器管理、看取り対応
対象エリアは、
練馬区
板橋区
中野区
杉並区
※具体的なエリアは問い合わせで確認が必要
城北さくらクリニック、自宅で治療したい、という方を医療面でサポートする体制が整っているため、ご本人だけでなくご家族にも心強い存在となります。
城北さくらクリニック
https://www.houmon-shinryo.jp
〒176-0001 東京都練馬区練馬1丁目18−8 犬丸ビル 3F
03-5912-0203
▲目次に戻る
3位:医療法人社団ときわ 練馬在宅クリニック

医療法人社団ときわ 練馬在宅クリニックは、東京都練馬区にあり、「日本中の誰もが質の高い医療を享受できる未来を目指して、人に寄り添い、未来に挑む。」を理念として掲げ、地域医療の柱となるべく訪問診療を中心とした診療所を展開しています。
2018年4月からは小児在宅医療も立ち上げ、高齢者に限らない全ての人が望む場所で自分らしく過ごすことができるように生活そのもののサポートを行うと同時に、全てのスタッフが「在宅医療の専門家」として高質な医療の普及に努めています。
年齢や性別、そして抱えている病気や障害によって制限を受けることなく誰もが自分らしく過ごす事のできる社会の実現がときわの使命です。
患者さん一人ひとりの生活や価値観を何よりも重視し、最適な医療を受けることができる環境を全ての人に提供致します。
医療法人社団ときわは、質の高い医療を日本中の誰もが享受できる当然の社会インフラとして整備し、全ての人が望む場所でその人らしく生きることのできる未来を目指します。
療法人社団ときわでは、0歳からご高齢の方までご年齢を問わず訪問診療をおこなっています。
何か所もの病院や診療科に通院しておりご負担に感じている方
通院してはいるが、「自分がどんな病気なのか」「どのような薬を飲んでいるのか」がわからず、不安を感じている方
処方されている薬が多く、服薬が大変になっている方
ご高齢でいつなにがあるかわからず、不安を感じている方
体調に不安があるものの、かかりつけ医と呼べる病院がない方
人生の最期まで自宅で過ごしたいと考えている方
訪問診療を利用したことがあるが、内容に不満を感じた方
現在入院中で、退院後はご自宅での療養を望んでいる方
現在入院中で、自宅療養は難しいといわれている方
悪性疾患の患者さんで、ご年齢を問わず、最期までご自宅で暮らしたい方
こんな方におすすめです。
医療法人社団ときわで診ている疾患例
高血圧、糖尿病、認知症、骨粗鬆症、脳梗塞、悪性腫瘍、慢性心不全、パーキンソン病、神経難病、COPD、廃用、老衰など
対応可能な処置、検査などの一例
呼吸管理
在宅酸素、気管カニューレ交換・管理、人工呼吸器(※要相談)
栄養管理
胃ろう管理・交換(バルーン型)、中心静脈栄養・ポート管理、経鼻経管栄養(※要相談)
排泄管理
膀胱留置カテーテル管理・交換、ストーマケア
疼痛管理
悪性腫瘍による疼痛コントロール(麻薬処方・携帯型精密輸液ポンプ管理)
処置
褥瘡処置、インスリン注射、点滴、胸水・腹水穿刺(※要相談)、輸血(※要相談)
各種検査
血液検査、超音波検査、心電図、尿検査、血糖測定、新型コロナウイルス検査(PCR検査・抗原検査)、インフルエンザ検査など
予防接種
インフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチン、肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンなど、通院が困難な方々のために、医師や看護師が定期的にご自宅を訪問し、内科診療や緩和ケアなどを提供します。
24時間対応
緊急時には24時間体制で対応しています。
チーム医療
医師、看護師、医療コーディネーターが連携し、包括的なサポートを行います。
地域密着型
練馬区を中心に、地域の在宅医療ニーズに応えています。
医療法人社団ときわ 練馬在宅クリニック
http://tokiwagroup.jp
〒176-0023 東京都練馬区中村北1丁目5−9 第二永崎ビル 1階
050-3823-2317
▲目次に戻る
4位:よしなが在宅クリニック

よしなが在宅クリニックは、東京都練馬区ある在宅医療専門のクリニックで、訪問診療や緩和ケアを中心に提供しています。
定期通院が困難な状態でご自宅や施設などで療養されている方は、どなたでもご利用いただけます。
よしなが在宅クリニックでは在宅医として多くの患者さんを診ています。
在宅医のやるべきことは、その価値観に寄り添うことだとよしなが在宅クリニックは考え、患者さまのご自宅に入れてもらう以上、ただ診察をするだけではなく、どうしたらその価値観に寄り添えるかを医療面からはもちろんのこと、介護や生活面からも考えていただけます。
癌の在宅緩和ケア
心不全・狭心症・心筋梗塞後などの心疾患
脳梗塞後・脳出血後・ くも膜下出血後などの脳血管疾患
喘息・COPDなどの呼吸器疾患
認知症・パーキンソン病などの神経疾患・精神疾患
糖尿病・高血圧・高脂血症などの生活習慣病
整形外科疾患
褥瘡・皮膚科疾患
内科・消化器疾患全般
外科疾患全般
対象の方
ご自宅や施設での医療を望まれる方
定期的な通院が難しくなってきた方
急な体調悪化時もご自宅や施設で診てもらいたい方
かかりつけ医のいない方
現在の生活や介護に不安がある方
様々な医療機器(点滴・尿道カテーテル等)があり、ご自宅での管理が不安な方
認知症に対するケアや医学的アドバイスを必要とされる方
病院から退院した後のケアが必要な方
ご自宅や施設で穏やかに過ごされたい方
ご自宅や施設でのホスピスケア(緩和ケア)を希望される方
かかりつけ患者様24時間365日サポート
夜間・休日もお電話いただければ、スタッフに転送されるようになっております。病状をお伺いした上で、必要に応じて往診や救急要請の判断をいたします。
診療科目
内科、緩和ケア内科、麻酔科、精神科、呼吸器科、消化器科、整形外科、神経内科、皮膚科、循環器科など
対応エリア
練馬区全域、中野区・杉並区・板橋区・和光市の一部地域
診療時間
月曜~木曜 8:00~18:00(訪問診療のみ)
対応体制
24時間365日対応可能で、夜間・休日の緊急往診にも対応しています 。
院長紹介 吉永惇一医師
名古屋市立大学医学部を卒業後、豊島病院、東京女子医科大学病院、日本大学医学部附属板橋病院、がん研究会有明病院、練馬総合病院などで勤務経験を積まれています。在宅医療においては、患者さまの多様な価値観に寄り添い、医療だけでなく介護や生活面からもサポートすることを大切にされています 。
よしなが在宅クリニック
https://y-zaitaku.clinic
〒176-0021 東京都練馬区貫井2-27-23 パラドール中村橋101
03-5848-9501
▲目次に戻る
5位:練馬区の訪問診療はホームメディカルクリニック

ホームメディカルクリニック(練馬区)は、東京都練馬区にある在宅医療を専門とするクリニックで、通院が困難な患者さんを対象に、医師が定期的に自宅を訪問して診療を行う訪問診療を提供します。
診療内容は内科を中心に、糖尿病・高血圧・心不全などの慢性疾患管理、認知症対応、緩和ケア(がんなど)など多岐にわたり、必要に応じて在宅酸素や胃ろう、カテーテル管理も可能です。
ホームメディカルクリニックでは、
病院との引継ぎを密接に行い、自宅で快適に過ごせるように努める
長い間救急医療に携わっていたため、外科系はもちろん、循環器・呼吸器・神経系疾患や糖尿病などの内科系疾患も対応可能で、処置や管理を適切に行う
看護師などとの連携により、褥瘡をはじめとした種々の処置や点滴などを行う
いままでの医療技術をもとに、個人に最も適したオーダーメイドの医療を目指す
体調が悪くなった際には、24時間相談あるいは往診に対応します。また、入院が必要な場合は、病院の手配をする
をコンセプトに、診療にあたり患者さまに治療内容を理解してもらい、納得してから治療を行うことが大切だと考えています
ホームメディカルクリニックが提供する4つの安心を提供しています。
1、
在宅医療は、毎月2回、決まった時間に訪問いたしますので、通院する負担も待ち時間もありません。
2、
当院の院長は、ホームメディカルクリニックを開院する前、救命救急センターに長年勤めていました。救命救急センターでは、急病の方を対象に診療科に関係なく診療を行い、治療の経過に応じて適切な診療科と連携して診療に当たっていました。その経験を生かし、患者さまの身体の状態を適切に診断し、地域の病院と連携しながら診療に当たります。
3、
在宅医療の最も大きなメリットは、その方の生活の場に寄り添った医療を提供できるという点です。それぞれの環境に応じたオーダーメイドの診療を行い、ご家族の方にアドバイスをさせていただくことができます。病院では疾病の治癒、延命治療が重視されがちですが、在宅医療では静かで安心できる療養生活を送りたいというご要望も叶えることが可能です。
4、
原則として決まった日の決まった時間にお伺いしますが、緊急時には24時間365日対応いたします。容体が急変した場合、患者さま・ご家族さまのご意向を充分に踏まえた上で、在宅のまま処置を行うのか、入院先を紹介するのかを判断します。入院先に特定の病院を希望される場合も対応いたします。
院長 菊地 充 プロフィール
昭和59年03月 帝京大学医学部卒業
昭和59年05月 岩手医科大学第1外科入局
平成02年01月 岩手県立宮古病院第1外科医長
平成04年12月 岩手医科大学高次救急センター助手
平成07年04月 亀田総合病院救命救急センター医長
平成10年01月 杏林大学救急医学教室助手
平成20年02月 ホームメディカルクリニック開院
練馬区の訪問診療はホームメディカルクリニック
https://www.hm-cl.com
〒177-0033 東京都練馬区高野台1丁目7−20 プレステビル 901
03-5923-6625
▲目次に戻る
訪問診療の内科って?

訪問診療とは、医師が患者の自宅や施設(介護施設など)を定期的に訪れて、内科的な診療を行う医療サービスのことです。
訪問診療では、一般的な内科疾患を中心に、循環器科、神経内科、精神科、整形外科、皮膚科、泌尿器科といった様々な診療科目の診療を受けることができます。
医師が患者さんの患者さんの生活環境で診察を行うため、適切な治療や生活指導を行えることがメリットです。
(診察や治療、薬の処方、生活指導まで行います。)
通常は2週間に1回や月1回など、計画的な訪問を行います。
一般的な内科のほか、クリニックによっては皮膚科や循環器科、神経内科、精神科などの専門的な症状にも対応しています。
訪問診療では、患者さんの状態や希望に応じて、通院との併用や完全在宅に切り替えるなど、臨機応変で柔軟な対応も可能ですが、「待ち時間が嫌」「通院が嫌」「他の人と会いたくないから自宅で診てほしい」といった理由で訪問診療を受けることはできません。
主な診療科目としては以下が挙げられます。
内科
風邪、発熱、吐き気、嘔吐、食欲不振、咳などの一般的な症状
循環器科
心不全などの心臓疾患の管理
神経内科
神経疾患の診療
精神科
認知症や精神疾患のケア
整形外科
関節痛や骨折後のリハビリテーション
皮膚科
褥瘡(じょくそう)の処置など
泌尿器科
カテーテル管理など
診療科目や医師の専門性はクリニックごとに異なり対応可能な範囲も変わります。そのため、患者さんの状態などに合わせて、適したクリニックを選択する必要が重要です。
特に通院が困難な高齢者や要介護者、在宅療養中で医療的な管理が必要な人、ご家族が医療面のサポートを自宅で希望している場合、家族の負担を大きく減らし、患者さんに寄り添うことが出来ます。
訪問診療の主な対象者は、自宅療養中で通院が困難な人です。たとえば、
病気や障害などによって歩行が困難、寝たきりなど病院への通院が困難な方
人工呼吸器や胃ろうなどを装着していて移動が困難な方
終末期療養や退院後の療養を自宅で行いたい方
自宅での看取りを希望されている方
退院直後で通院が困難な方
精神疾患で外出が困難な方
外来治療では対応が難しく、入院するほどではない、という方にとって、在宅での個別のプラン、カスタマイズが可能で、治療の向上、生活支援、生活レベルの向上など、その需要は大きく広がっています。
訪問診療の内科で主に行われること
定期的な健康チェック(血圧・脈拍・呼吸・体温など)
慢性疾患の管理(糖尿病、高血圧、心不全、COPDなど)
処方箋の発行と服薬管理
必要に応じて検査(血液検査、尿検査、心電図など)
症状の変化への対応や緊急時の対応(※緊急往診とは別)
看取り医療(ターミナルケア)も対応可能な場合が多いです
対象となる疾患の例:
糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病
認知症
呼吸器疾患(例:COPD、肺炎)
心疾患(例:心不全、狭心症)
脳梗塞の後遺症
がんの終末期医療
精神疾患
▲目次に戻る
どんな病気を診てくれるの?

訪問診療の内科では、通院が困難な高齢者や障害のある方などを対象に医師が自宅や施設を訪問して診療を行います。
一般的な内科と同様に幅広い疾患に対応しますが、訪問診療ならではの生活指導など包括的なケアを行います。
以下に、訪問診療内科でよく診られる疾患・状態を詳しくご説明します。
訪問診療の内科で診る主な疾患・状態
悪性腫瘍:肺癌、胃癌、大腸癌、胆管癌、膵癌、卵巣癌、乳癌など、在宅緩和ケアを必要とするすべての癌。
神経疾患:脳梗塞・脳出血後遺症、パーキンソン病・パーキンソン症候群、多系統萎縮症などのいわゆる神経難病。
呼吸器疾患:肺気腫(COPD)、間質性肺炎、肺結核後遺症など。
心血管疾患:慢性心不全、各種弁膜症、狭心症・心筋梗塞後など。
消化器疾患:経口摂取困難(胃瘻・腸瘻造設状態・中心静脈栄養カテーテル留置状態)、肝硬変など。
腎泌尿器疾患:慢性腎不全、尿道カテーテル留置状態など。
整形外科疾患:脊髄損傷、胸椎腰椎圧迫骨折後、大腿骨頸部骨折後、脊柱管狭窄症など。
自己免疫疾患:関節リウマチ、全身性エリテマトーデス(SLE)、強皮症など。
各種障害:小児麻痺、発達障害
など、ほかクリニックの医師の専門分野等により差があります。
また内科以外にも皮膚科、アレルギー科、精神科、心療内科などにも対応している場合もあり、従来の訪問診療より、よりニーズ・需要とともに、その医療提供のあり方も変わってきています。
訪問診療では、上記に代表される疾患で、通院が難しい患者様(施設)に訪問診療を行い、また生活支援したり、ご家族の負担を減らすなど、現代に欠かせないものとなっています。
▲目次に戻る
自宅まで来てくれるのですか?

訪問診療では、定期診療と言って決まったスケジュールに医師が訪問してくれます。
定期診療:月1回または2回が一般的
またそれとは別に365日24時間対応の緊急往診がある場合が多いです。
緊急往診:急変時には24時間対応(対応している医療機関に限る)
基本的には在宅医療は、通うのが困難であるという方が対象となりますが、
病気の治療だけが目的ではなく、ケアマネージャー、訪問看護、訪問介護、調剤薬局など、種々の専門職がチームで連携し患者さんが安心した療養生活ができるよう包括的なサポートを指します。
外来に行ける状態でなく、それを無理して続けると、治療が効果的でなくなったり、生活上どのようなことに困っているか具体的に分からなかったりします。
訪問診療では面談やヒアリングなどを通し、療養計画を立てていき、定期な診療やそれを包括するサポートなどを加え、治療や生活支援など、患者さんにより寄り添ったに医療の提供を行います。
また、医療機関、クリニックにより対応エリアが違うので、公式サイトで確認すると良いでしょう。
訪問診療で受けられる医療内容
診察、処方、病状説明
採血・検査(血液検査、尿検査など)
点滴や注射
在宅酸素・吸引など医療機器の管理
床ずれ・創傷の処置
緩和ケア・看取り支援
医療・介護相談、各種書類作成(主治医意見書、診断書など)
▲目次に戻る
費用は保険適用内ですか?
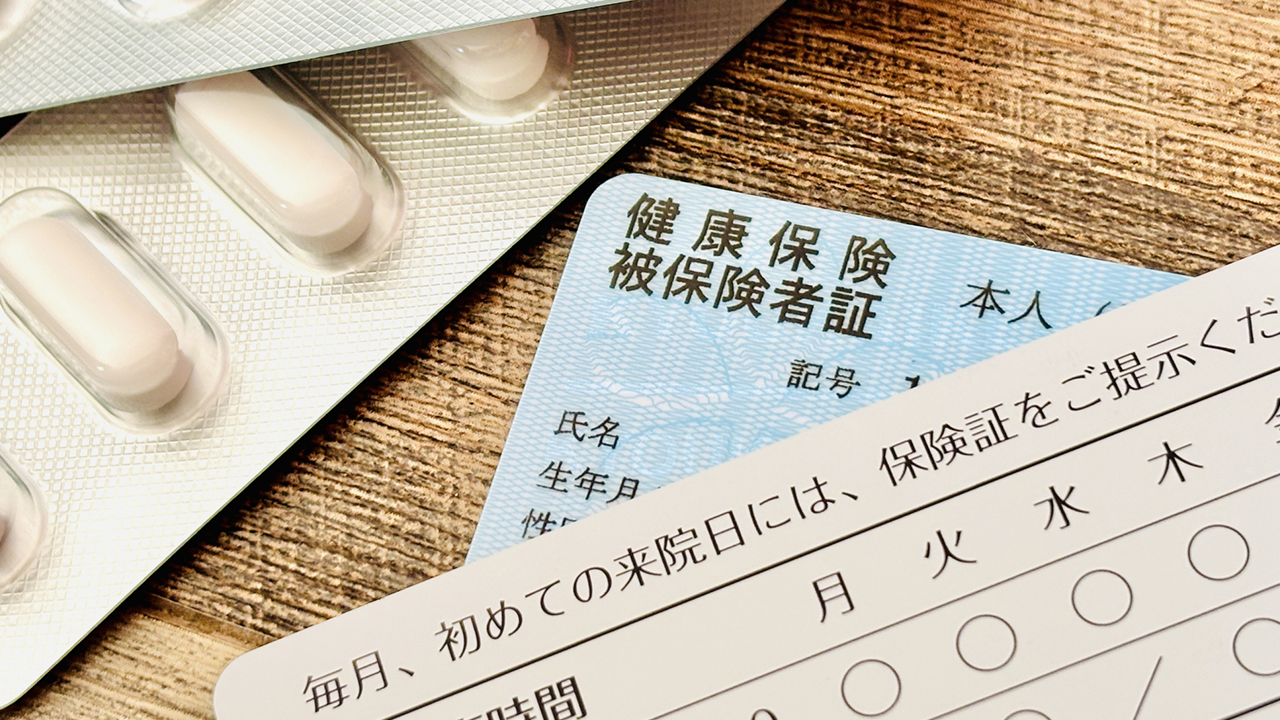
訪問診療の内科でかかる費用は、保険適用内になるため基本的に1~3割負担となります。
実際の費用は基本診療費・追加の診療費に分けられ、利用者ごとの医療負担割合に応じて算定します。
以下に、費用の構成や目安をわかりやすく詳しく説明します。
基本診療費とは、利用者の症状に合わせて医師が治療計画を立て、その計画に基づいて行われる医学的管理の料金と、訪問診療の際にかかる料金です。
医学的管理の料金は「在宅時医学総合管理料(在医総管)」訪問診療にかかる料金は「在宅患者訪問診療料」または「訪問診療料」などとして請求されます。
在宅患者訪問診療料は重症度や月の訪問回数、在宅患者訪問診療料は原則週3回の算定を限度として(例外あり)、算定する仕組みです。
ただし、がん患者の方については「在宅がん医療総合診療料」として、管理料や訪問診療料を分けずに包括的な料金が請求されます。
追加の診療費
追加の診療費とは、基本診療とは別に行われる検査や処置にかかる費用です。
追加の診療費に含まれる項目の一例は次のとおりです。
各種検査(血液・尿・便・痰・心電図)
点滴・注射
ワクチンの接種
書類作成
往診
医療機器の使用
抗がん剤治療
訪問診療では、利用者の状況に応じて検査や処置を実施します。血液検査や心電図検査のほか、点滴や注射、酸素吸入器のような医療機器の使用なども追加の診療費に含まれます。
費用の目安(自己負担1割の場合)
以下は、月2回の定期訪問を受けた場合のおおよその金額です(高齢者、1割負担の場合)
定期訪問診療(在総管あり) 約5,000〜7,000円
処方・検査あり 約1,000〜3,000円追加
合計(概算) 約6,000〜10,000円/月程度
※ 処置・検査・点滴が頻繁にある場合や、緊急往診を受けた月はこれより高額になることがあります。
その他にかかる費用
処方薬の費用 調剤薬局に支払う薬代(保険適用)
医療材料費 カテーテルや吸引チューブなどの材料費(保険対応可)
交通費 医療機関により異なる(無料〜数百円/回)
訪問診療を受ける方やご家族は、次のような制度が利用できます。
医療費控除
1年間の医療費が**10万円以上(所得によって異なる)**かかった場合、確定申告で所得税の還付が受けられる場合があります。
高額療養費制度
月間の医療費が一定額を超えると、超過分が払い戻される制度があります(所得や年齢に応じた限度額があります)。
公的助成制度も活用可能
状況に応じて、以下の制度が使えることがあります:
高齢者医療制度(後期高齢者) 75歳以上(または障害で65歳以上) 原則1割または3割負担
障害者医療費助成 障害認定を受けた方 自治体により負担免除あり
生活保護 保護を受けている方 自己負担なし
難病医療費助成 指定難病の方 所得に応じて軽減あり
▲目次に戻る
訪問診療の内科によりどんな差があるの?
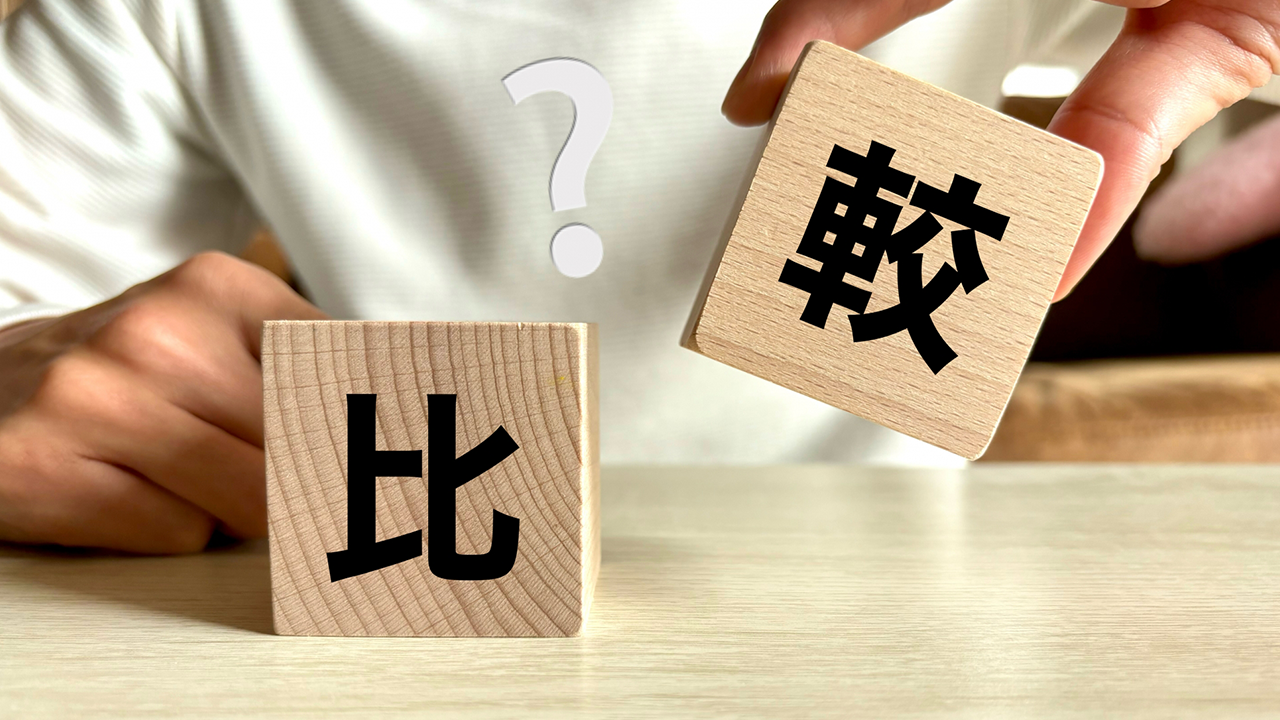
訪問診療の内科は医療機関・クリニックによってサービスに大きな違いがります。
特に大きく分かれるのは医師のこれまでの経験や専門分野、得意分野です。
実際に患者を診るのは医師になりますから、どういった対応ができるかなどは、医師の腕の差があります。
逆にいうと、専門分野や得意分野が広く、その対応の広さや新たな試み(現在の患者様のニーズに合わせた新たな治療)などそういった部分を強みとしている場合も多くあります。
医療機関・クリニックが備える設備やスタッフ、連携しているケアマネジャー、訪問看護、訪問薬剤師、栄養士なども違います。
また、医師そのものとの相性や臨機応変な対応力などなどもあります。
ほか、治療方針、処置の範囲、検査、医療機器の対応、訪問回数、スケジュールの柔軟性、 緊急時の対応などが違います。
訪問診療の基本は在宅医療ですから、ご自身に合った医療機関・クリニックを選ぶことが大切です。
どんなんことで悩んでいるか、困っているのか、どのようなものを望むか、などしっかりお話し、ご自身が納得できることがポイントです。
またご家族様にとっても安心してお願いできるかどうかも重要です。
そういったコミニューケションがスムーズか、丁寧か、親身になってくれるか、なども大切でしょう。
訪問診療の内科は内科疾患に限らず、皮膚科、精神科、心療内科など幅広く対応するクリニックも増え、昨今では精神疾患が増えており精神科、心療内科を得意とする内科もあります。
また、多くのかたが地元の医療機関・クリニックから選択することから、口コミ・評判も得やすいでしょう。そういった実際の利用者の声や口コミ・評判を収集することも1つの指標となるでしょう。
▲目次に戻る
どういった方が利用されているの?

訪問診療の内科は、高齢者の方や体の不自由な方、在宅での療養中の方など、ご来院が難しい方などが利用されています。
患者さんの健康状態の把握と適切な医療を提供し、快適な生活と健康維持をサポートしてします。
訪問診療を利用する人の特徴は、通院が難しい、困難である、在宅療養をしているといった方が多いことが特徴です。
特に高齢の方は、体力低下、体への負担が大きい、歩行が難しい、家族の付き添い困難、などがあります
また認知症で、病院にたどり着けない方、
脳梗塞・脳出血、慢性疾患、難病で在宅医療が必要と認める方な方、
障がいや精神的な事情で外出に困難が伴う方、
(発達障害や精神疾患の影響で外出が困難)
などです。
中心核となるのは、やはりご高齢の方、が多いというのが現状ですが、疾患によっては若い方でも利用されます。
通院が難しい、というのは一般的にあまり理解をえられにくい部分です、
ですが患者様は、
自宅で治療や療養を続けたいという希望がある
病院に行くのが困難を伴う
医療と介護の両面からサポートを必要としている
家族の負担軽減を図りたい
定期的な健康管理と急変時の対応体制が欲しい
などの悩みや困りごとを抱えており、
地域に密着し多くのかたが利用されているのが特徴です。
▲目次に戻る
外来も行っているのですか?

訪問診療の内科でも外来診療を行っている医療機関・クリニックは多くあります。
外来と訪問医療を兼ねている医療機関・クリニックはハイブリッド型と言われ、外来と在宅、双方の強みを活かしています。
どちらかというと、
今後の治療次第で、外来に切り替えが期待できる場合、希望されている場合、訪問診療だけでなく外来も利用されたい方が多く利用されます。
外来も行っている場合、医師や看護師の体制が比較的充実していたり、訪問診療/外来の切り替えの相談も可能で、多くの場合、外来で利用していたが、訪問診療に切り替えた、というケースが多いようです。
患者様にとって長くお付き合いしている医師に診て欲しいものです。
そのため、転院などもなくスムーズな切り替えが可能です。
それとは別に完全訪問診療専門の医療機関・クリニックもあります。
どちらかというと、
このまま在宅での医療を続けていきたい、外来の希望はない、という方が多いようです。
ハイブリッド型が柔軟型とすれば、
完全訪問診療専門は、とにかく在宅で(寝たきりなど)、という場合が多いです。
医師の数、備える設備や、連携しているケアマネジャー、訪問看護士、訪問薬剤師、栄養士などの体制はどちらがというわけではなく、
医療機関・クリニックによります。
大まかに、
外来に切り替える予定がある ハイブリッド型
とにかく在宅で問う方は 完全訪問診療専門
それとは別に往診と言って、緊急時の場合でも、医師が訪問し、受診ができるようになっていることが一般的です。
▲目次に戻る
電子カルテとは?

訪問診療の内科における電子カルテは、IT技術を活かし、外来におけるカルテとは、異なる特有の運用になっています。
患者様の診療情報をデジタル化したものを電子カルテと言い、医療チームとのリアルタイムな情報共有が可能となります。
それにより、訪問診療では、患者さんの自宅や施設で必要な医療をより正確に提供します。
医師や看護師がノートPCやタブレット端末を使って、訪問先で電子カルテを記録するため、個別のニーズに合わせたケアを提供できるようになります。
訪問診療では、クラウド型(オンライン型)の電子カルテが多く使われています。
その利点は、自宅や施設など院外からもアクセス可能、医師・看護師・事務スタッフ間での情報共有がスムーズになる、外部連携となる訪問看護、薬局、ケアマネージャーとの連携に対応する、など多くあります。
記録内容は、
患者のバイタル(血圧・体温など)、主訴・診察所見・診断
処方・注射・点滴などの指示
処置内容(褥瘡処置、胃ろう管理など)
家族や介護職への指示・相談内容
訪問看護やケアマネージャーとのやり取りの記録
他
など多岐にわたります。
これまでは紙媒体への記録が中心でしたが、電子化することで、細かい記録も見落とさず、より綿密な分析も出来るため、患者様の治療からケアまで、より寄り添った医療を提供出来るようになります。
▲目次に戻る
訪問診療の内科のメリットをズバリ教えてください

訪問診療の内科には、患者さんにとってどんなメリットがあるでしょうか。
現在の日本は高齢化社会が進んでいるという点、また精神疾患などの新たな疾患の増加があります。
その病気の陰には、患者さん本人しか分からない困りごと、悩み事があります。
例えば、今日、通院したいが、体調が悪く通院できない。
これがなかなか周囲の方には理解してもらえないなどがあります。
しかし訪問診療の内科医師に相談すればそういった面も理解が得られ、具体的な治療方針などプランニングをしてくれます。
逆にいうと訪問診療がなければ、通院に行けない、で終わっってしまい病気を放置してしまう事態につながります。
訪問診療は在宅で医療を受けたいという患者さんの想いに応える唯一の方法です。
それは大きなメリットと言えるでしょう。
また、医師が治療や療養のプログラムを立ててくれたり、話し合いの中で調整出来ることもメリットです。
また、診察だけでなく、健康管理・検査などを受けられることも実施されます。
体の内側は検査などしなければ分かりませんから、定期的に実施することによる安心感を得られるでしょう。
他、薬の処方、薬の調整、血液検査、点滴、※褥瘡 処置なども対応で、これらは病状の安定や予防的なケアにつながります。
※寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうこと
また、患者さんのご家族もその介護などで大きく疲弊してしまうことがあります。
ケアマネージャー、訪問看護師、訪問薬剤師、栄養士などと連携したチーム医療が可能なため、その負担を大きく減らすことができます。
また、医師が定期的に訪問してくれることで、ご家族の安心感も大きくなるでしょう。
もっとものメリットはそういった取り組みの中で、医療と繋がっていれること、つまり困った時に相談できるプロがいるということ、それは患者さん、ご家族さんにとって大きな安心感につながります。
▲目次に戻る
訪問診療で診て貰えるのは内科だけですか?

訪問診療では内科が基本になりますが、内科以外の診療にも対応しています。
例えば、内科でも循環器内科、呼吸器内科といった、専門性の高い診察・治療が受けられますし、耳鼻科や眼科、整形外科、皮膚科、精神科などの科目の受診も可能です。
例えば、複数の診療科に通われていた患者さんの場合、訪問診療に集約することが出来ますが、それぞれの医師が変わってしまうというデメリットもあります。
しかしながら、訪問診療を受ける患者さんは病院に行くことが困難を要すため、集約することで同時進行での、包括的な治療、ケアを受けることができる、というメリットにもなります。
例えば、精神科・心療内科では、認知症による幻覚・妄想・徘徊、うつ状態、不安障害、統合失調症など
外科・皮膚科でいうと、褥瘡のデブリードマン、小外科処置、皮膚トラブル(湿疹、かぶれ、皮膚感染症)
整形外科では、骨粗しょう症、関節炎、リウマチの診断・疼痛管理
歯科では、義歯の調整、虫歯治療、口腔ケア
泌尿器科では、尿道カテーテル管理、前立腺肥大、排尿障害の薬物治療、尿路感染症の対応
神経内科では、パーキンソン病、ALS、脳梗塞後遺症などの慢性神経疾患
など、患者さんのニーズに応じて幅広く対応することが一般的です。
▲目次に戻る
オンライン診療も可能ですか?

訪問診療の内科でもオンライン診療を提供しているケースがありますが、まだ一部という状況です。
医療機関によって実施状況は異なり、主に病状が軽度の場合に限ることが一般的です。
オンライン診療とは、訪問診療を基本としながら、補助的に使うが一般的です。
また疾患によって制限があるため、オンライン診療ができないものもたくさんあります。
そのため、オンライン診療が行えるかどうかは実際に医師に確認をすることが必要です。
オンライン診療とは、スマートフォン・パソコン・タブレットのビデオ通話やチャットで、問診・診察・処方までをインターネット上で行う診察・治療方法で、今後オンライン診療の拡大は、注目されています。
またスマートフォン・パソコン・タブレットでのオンラインシステムを使うため、安定した通信環境が必要になります。
オンライン診療が認められるのは、症状の安定が継続しており、処方だけで済むときや、体調相談に活用するケースもあります。
そのほかご家族との相談、緊急対応の判断などに使用される場合もあります。
ですが、オンライン診療を受けるには訪問診療実績があることなど制限があります。また初診からのオンライン診療は不可。
あくまで、訪問診療で継続的に診ている患者さんに対しての補助としてオンラインを併用という形になります。
また、病状によっては、患者さんが希望しても、医師の裁量により利用ができない場合もあります。
オンライン診療が全国的に普及しているかというと、都心部のクリニックに多いものの、地方ではなかなかまだ普及していない、という現状と、やはり診療は医師と実際に会って診察するのが基本という概念が強いとも言えます。
▲目次に戻る
在宅医療って何ですか?

在宅医療とは患者が自宅などで受けるすべての医療サービスの総称です。
在宅医療=「訪問診療を含む」もっと広い枠組み、と覚えると良いでしょう。
在宅医療は医師だけでなく、看護師、薬剤師、理学療法士、歯科医師など、複数の専門職による多職種連携で支えられます。
例えば、
訪問診療(医師)
訪問看護(看護師)
訪問リハビリ(リハビリ職)
訪問薬剤指導(薬剤師)
訪問歯科診療(歯科医師)
緩和ケア(末期がんなど)
小児在宅医療
これらを総称して在宅医療と呼びます。
在宅医療の対象となる人は、
高齢で通院が困難な人
末期がんや難病患者
脳卒中後の後遺症がある人
認知症で外出にリスクがある人
小児在宅医療(重度の障害をもつ子ども など)
などです。
訪問診療だけでなく、
医療と介護などの連携により、患者さんのベッドを自宅とし、患者さんらしく、包括的なケアができることが在宅医療と言って良いでしょう。
▲目次に戻る
支援制度などもあるのですか?

訪問診療には公的な支援制度や費用補助があり、患者さんやご家族の経済的負担を軽減するしくみがあります。
医療保険(健康保険)
訪問診療は、通常の外来診療と同じく保険適用になります。
年齢や所得に応じた自己負担(例:70歳以上で原則1〜3割負担)が適用されます。
高額療養費制度
あまり聞き慣れないかもしれませんが、医療が高額になり支払えない金額になる場合が多くあります。
高額療養費制度は月々の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されるため、負担を大幅に減らすことが可能です。
負担額は所得額に応じて限度額が異なります。
介護保険制度
医師から要介護認定を受けた場合、介護保険制度を利用することが出来ます。
訪問診療そのものは医療保険で行われます。
その他高額になる訪問看護やリハビリ、福祉用具など介護系サービスと併用する場合は介護保険が適用されるので安心です。
介護保険では、限度額内で1割(〜3割)の負担です。
在宅療養支援診療所・支援病院制度
国が制度化した「在宅療養支援診療所(機関)」では、24時間体制の訪問診療や緊急往診、看取り支援が受けられます。
この制度に基づく医療機関を選ぶことで、より手厚い支援をしてもらうことが可能になります。
障害者医療費助成制度
障害者手帳を持つ方などに対し、自治体が医療費を助成する制度。
自己負担分が軽減される場合があります。
小児慢性特定疾病医療費助成・難病医療費助成
小児や特定の難病を持つ方には、国や都道府県が医療費の一部または全額を助成。
地域包括支援センター
患者さんやその家族が相談できる公的窓口。制度の申請支援を行う場所。
ケアーマネージャー
介護保険のサービス調整や介護必要な支援の提案や関係機関との繋ぎ役をしてくれる。
医療ソーシャルワーカー
患者さんにとっての相談役で、困りごとを相談したり、制度の案内、関係機関との繋ぎ役。
特に各申請に当たっては、申請の書式そのもの難しかったりするので、作成の手助けもしてくれる。
▲目次に戻る
現在の医療ニーズはどう変わっていますか?

現在の訪問診療のニーズは、社会構造の変化や医療の在り方の見直しにより、急速に拡大・多様化しています。
その背景には高齢化の加速が大きいでしょう。
現在の日本は65歳以上の人口が29%超と約三分の一に上ります。
ご高齢になると何かしらの病気を抱えていたり、通院が困難な患者さんも多くなります。
特に核家族化が高まり、ご高齢の方が一人暮らしされていることも少なくありません。
その時にどうしても必要になるのが訪問診療の存在になります。
またこれまでの病院中心から自宅中心への移行が大きいでしょう。
医療・介護・住まい・生活支援の一体化が進み、住み慣れた自宅で療養したいとう患者さんが増えています。
これによって自宅の療養により患者さんの負担を軽減できます。
例えまた退院後の自宅の訪問診療にスムーズに移行できるなどのメリットもあります。
他、小児・障害者・難病患者の拡大もあります。
重度障害児・慢性疾患の小児も自宅療養が可能になったり、例えば精神疾患障害など、地域生活支援が活性化しています。
高齢者中心から高齢者以外にも対象が拡大しています。
医療や介護の提供も医師・多職種の高度なチーム体制が求められるケースも増えていると言えるでしょう。
在宅医療専門クリニックや在宅療養支援診療所も増加を続けており、IT(情報通信技術)を活用したオンライン診療やデータ連携も進行、チーム制・看護師の役割強化も進展しています。
その多様化の中にも根底には「患者さんに寄り添った医療・介護」を提供し、負担を軽減したい、患者さんも自分らしく、という新たな文化が進んでいると言えるでしょう。
▲目次に戻る
こんな症状は訪問診療の内科へ
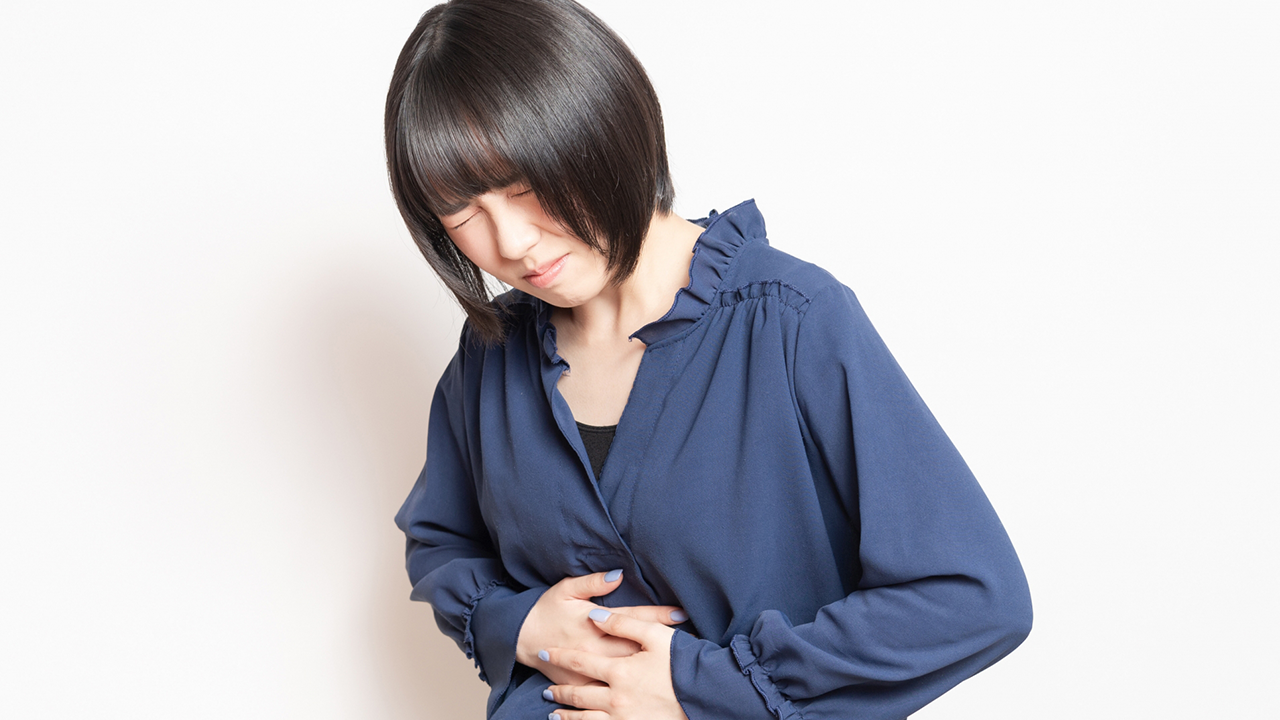
病気が長引くと、足腰が弱ったり、体力が低下したり、疲労で辛くなってしまう、そういった方に訪問診療の内科は大きな助けになるでしょう。
その症状は疾患により多岐に渡ります。
自宅による慢性的な疾患の治療や、管理や症状のコントロールを行う、と分かり易いでしょうか、外来でなかなか治療効果が出ないという方でも、療養状態が続くと症状が緩和したり、精神的な負担も軽減します。
また症状が厳しく訪問診療の内科で、という場合もネガティブではなく、上手に活用することにより、外来に切り替えていける場合もあります、また、自宅療養が続く場合でも、より自分らしい生活を送れたり、大きく負担となっていたものが取れてきたり、というメリットはあります。
一番大きいのは、医療のプロである、医師の治療を手厚く受けられることでしょう。
どのような症状、疾患であれ、医療の診察が必要です。
その治療や服薬、処置などにより、すごく厳しいと思えていた症状も緩和していくケースも珍しくありません。
なので、通院が厳しいと思った方は、訪問診療の内科が向いていると言えます。
また要介護認定を受けた方は、医療+介護でより専門性の高い包括てケアが可能です。
逆にいうと、
通院が問題なく可能な人はあまり向いてないかもしれません。
▲目次に戻る
メンタル不調も見てもらえますか?

訪問診療の内科でもメンタル不調への対応は可能です。
うつ状態、不安症状、慢性疾患に伴う抑うつなどがそれにあたり、例え精神的な疾患でも通院が困難になる場合はあります。
ただし、医療機関・クリニックにより範囲や対応の深さが変わるため、重度の場合は、より専門的な医療機関を選ぶ必要がある場合もあります。
メンタルの不調に対しては服薬や薬物調整、ヒアリングが中心となります。
症状が中程度の場合、十分な効果が出るや軽快に至る場合もあります。
重度のうつ病や統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、アルコール依存症、パニック障害・PTSDはより専門店な訪問精神科の方が良いでしょう。
治療の進め方としては、
服薬や経過確認で、要介護認定の患者さんの場合、医療と介護の双方から包括的なケアが必要となります。
メンタル不調の場合、医師の経験や専門性により腕の差があるので、そういった点も加味して、利用すると良いでしょう。
▲目次に戻る
診療時間はどうなっていますか?
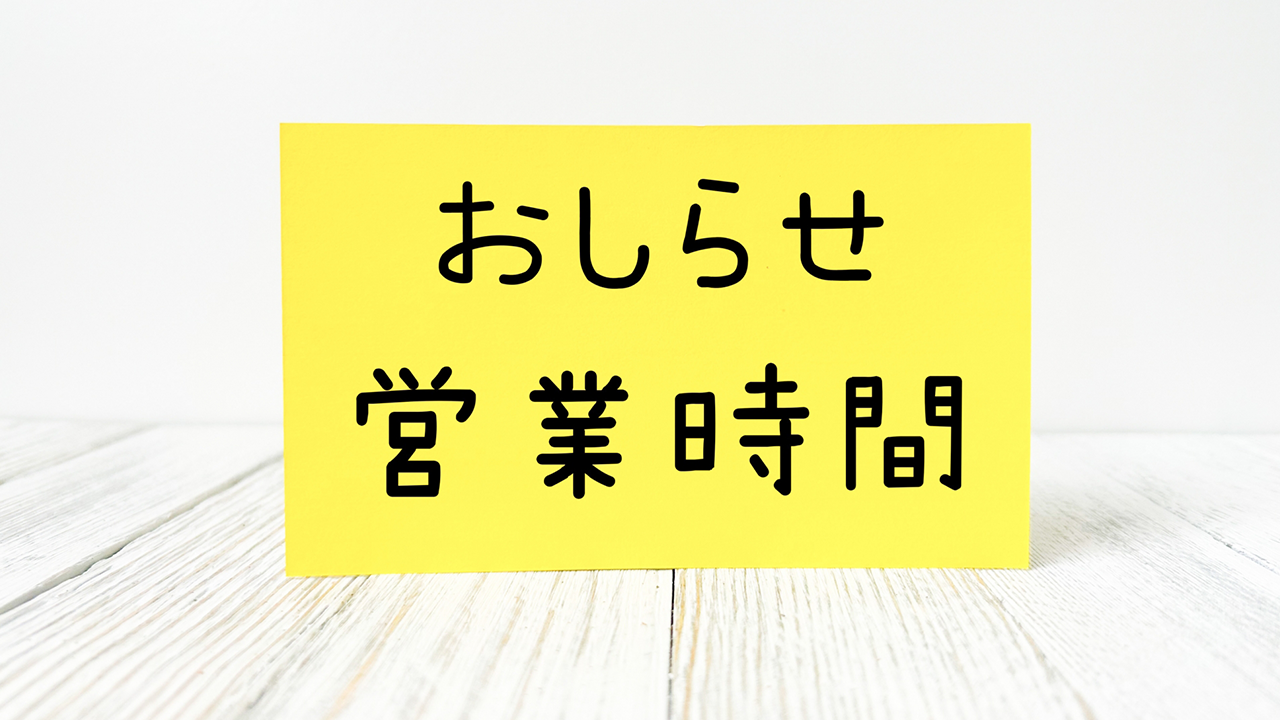
訪問診療の内科の診療時間は、通常の外来診療とは異なり、個別のスケジュールに基づいて行われるのが特徴です。
診療は主に、
定期訪問診療
臨時往診
に別れ、
定期訪問診療の場合、定期的な訪問でスケジュール化され、一般的には9:00〜17:00内です。
また、土日祝に対応しているかどうかは医療機関・クリニックによるので確認が必要でしょう。
臨時往診は患者さんの体調変化などで、24時間対応になっている場合が多いです。
夜間や深夜の定期訪問診療はありません。
また、定期訪問の時間は、患者さんの状態に応じて調整があるため、柔軟に対応している場合が多いと言えます。
「在宅療養支援診療所(在支診)」や「在宅療養支援病院(在支病)」の場合、24時間365日対応可能な体制が義務づけられています。
電話対応が夜間・休日でも緊急連絡が可能であったり、緊急往診が必要に応じて医師が自宅に訪問してくれたりと、より専門的なチーム体制がと整っているので安心です。
また、訪問診療と外来のハイブリッド型の場合、外来診察も行っています。
その場合、定刻で病院は解放しているため、今日は外来で診察を受けたいなども可能です。
外来の診療時間は医療機関・クリニックにより差があるのであらかじめ確認すると良いでしょう。
訪問診療は医師と患者さんの対話が最も重要です。
そのため、医師の考えと患者さん希望などコミニケーションを得ながら、柔軟に進められていくことが一般的です。
▲目次に戻る
訪問診療の内科が患者様にできること

訪問診療の内科が患者様にできること。
それは相互理解と信頼かもしれません。
医師や介護チームなどができることは我慢せず伝えてほしいという事。
些細なことでも、例えば、だるい、眠れない、など、体調の小さな変化を互いに共有する事ことからより良いケアに繋がっていきます。
もし我慢して伝えられない、それではなかなか良い治療に向かわない可能性があります。
なんでも相談して、例えば症状が緩和すれば、相互理解が深まります。
また早めの連絡で、入院や重症化を防げることがほどほどです。
訪問診療は長いお付き合いになることが多く、信頼がベースです。
互いにしっかり話し合い、一緒に納得しながら進めていける関係が重要です。
その中で、患者さんなりの納得の答えが出てくるものと考えます。
また訪問診療では医師だけでなく、ケアマネジャー、訪問看護師、薬剤師、リハビリスタッフなど、多職種が連携して患者さんを支えています。
患者さんに限らず、ご家族の観察や支援は、在宅療養の大きな柱になります。
患者様+ご家族+医療・介護チーム」で1つのチーム。
病気のことだけにとらわれず、暮らしや願いも教えて欲しい
訪問診療の目的は「病気を診る」だけでなく、その人らしい生活を支えることです。
そういった願いも最初は叶わなくとも、だんだんできるようになっていくからです、医療の方針もその人に合わせてカスタマイズできます。
一緒によりよい在宅療養をつくるという気持ちでいてほしい
訪問診療は診察するだけの関係ではありません。
患者さんの喜びが医師や介護チームの後押しになります。
互いに寄り添い合い、信頼し合いながら、よりよい形の医療・生活を一緒につくっていくことが理想です。
病気があっても、“その人らしく”暮らせるように、一緒に考えていきたい。
それが訪問診療に関わる医療者のいちばんの願いなのではないでしょうか。
▲目次に戻る
現代美の意識が上がっているのは何故ですか?

訪問診療の内科の患者さんの美への意識は高まっています。
それは例え在宅であっても、自分らしい表現をしたい、お洒落を楽しみたい、髪型を変えてみたい、昨今は特に新しいファッションや、化粧品、コスメなど多く広がっています。
なので、在宅だから、美への関心がない、というのは稀で、自分らしさの一環と言えるでしょう。
女性は綺麗でいたい、男性はカッコよくいたい、それはごく自然なことだと言えます。
また、医師・看護師・介護士などの他者と定期的に接することで、身だしなみへの意識が復活します。
他者とのつながりが戻ることで「清潔感や身だしなみに気を遣いたい」という気持ちが自然と芽生えます。
QOL(生活の質)重視の医療が広がっており、訪問診療では治療だけでなく、その人らしい暮らし=QOLの維持向上が大きな目標です。
清潔感、整容、外見のケアもQOLの大切な一部として重視され、美容やおしゃれに対するケアの意識も高まります。
たとえば、通販、訪問美容、訪問ネイル、在宅フットケア、訪問カットなどの在宅サービスも増える一方で、そういったものを活用する場面も多くなっています。
▲目次に戻る
訪問診療の内科 利用者の声

利用者の声を見ていくと、
通院がなく、先生が家まで来てくださることが何よりの安心です。
夜中に熱が出たときも、電話で相談できて本当に心強かった。
など家にいても医師に診てもらえる安心感や、特に夜間や休日の24時間対応への感謝の声が非常に多いようです。
また、
診察だけでなく、まるで家族みたいな存在です。
看護師さんが『お変わりありませんか?』と笑顔で来てくださるのが嬉しい。
など、医師やスタッフの人柄が良いなどのお声も多いようです。
忙しくなかなか時間が取れないが、おかげで家族の負担も減りました。
と、ご家族の安心や負担軽減も多いようです。
特に注目したいのは生活の質(QOL)向上です、
最近は散歩をしたり、趣味の映画鑑賞もできて嬉しいです。
最近は、読みたい本がたくさんあり、全部読みました。
など、一見ごく普通のことに思えるかもしれませんが、ご本人様の楽しみが増えるというのは、有意義と言えるでしょう。
このように、まとめていくと、
医療と繋がっていられる安心感やQOLの向上などに利用者さんのお声は集まっているようです。
▲目次に戻る
